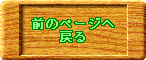
星総合病院心臓病センター
心臓血管外科
| <患者さん向け> |
| スタッフ紹介 |
| 入院案内 |
| 医療相談コーナー |
高橋 昌一(たかはし しょういち) 心臓血管外科部長 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ [略歴] 88年 弘前大学卒業. 92年 弘前大学大学院卒業後,米国ピッツバーグ大学胸部心臓外科研究員,米国ハーバード大学医学部ボストン小児病院心臓外科研究員,青森労災病院副部長,青森県立中央病院副部長,弘前大学助手,福島県立医科大学講師を経て,04年10月より現職 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ [学位] 92年 弘前大学医学博士 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ [資格] 日本外科学会認定医・指導医 日本外科学会外科専門医 日本胸部外科学会認定医 日本心臓血管外科専門医機構専門医 日本心臓血管外科学会国際会員 |
外来受診および入院・手術などについて
| 外来受診 |
内科医より当院での手術を勧められた患者さんは、まず当科外来を受診して頂くことになります。また、病状等により、入院先より転院して頂くことも可能です。 また、他院で手術を受ける予定の患者さんが、セカンドオピニオンをお聞きになりたい場合でも受診が可能です。この際、可能な限りデータなどをご持参頂ければ幸いです。 外来診療は、毎週月・水・木・土曜日午前中ですが、出張等により休診となる事がありますので、あらかじめ外来予約センター(0120−33−4895)または当科外来受付(024−923−3711内線212)まで予約・お問い合わせください。なお予約制になっておりますが、予約がない方でも受診が可能です。 |
| 入院 |
| 手術予定日を決めさせていただいた後、その1週間前を目安に入院日が決まります。入院当日は、外来にお越しください。その後、入院手続きの方法や手術までのスケジュールなどについて、担当看護師より説明があります。 |
| 入院後手術まで |
| 循環器病棟への入院となります。入院後は、手術に向けて、検査や薬の調節などを行います。また、手術前にご家族に、手術について詳しく説明させて頂きます。 |
| 手術 |
| 患者さん個人の症状・体調等に合わせた手術を行います。一般的な手術については、少し詳しくなりますが医療従事者向けページ(こちら)をご覧下さい。 |
| 手術〜CCU入室 |
手術当日は、手術室に予定時刻に入室し、まず麻酔科の医師により全身麻酔処置や点滴、心電図、血圧計の準備などが行われます。その後、準備が整い次第、手術を開始いたします。終了時刻は患者様により異なります。手術後は、CCU(Coronary Care Unit)に入室いただきます。ここで麻酔から覚めれば、人工呼吸器をはずし、強心剤などのお薬を減量していきます。その後、飲水や食事ができトイレまで歩行できる状態にまで回復すると、循環器病棟に帰室となります。CCU滞在日数は患者さんにより異なりますが、2-3日程度です。 |
| 循環器病棟帰室後から退院まで |
| 病棟帰室後は、症状にあわせナースステーションに近いお部屋に入って頂きます。その後、点滴の調節などを行いながら、術後リハビリテーションを行います。さらに、術後各種検査(血液検査、レントゲン撮影、心エコーなど)を行い、異常がなければ退院となります。退院までの期間は患者さんにより異なりますが、手術の日から10-20日間程度です。状況により、紹介病院などへの転院も可能です。 |
| 退院後 |
| 退院後は、お薬の調節などを行うために、当科外来、または紹介病院の外来などへの通院が必要となります。 |
| 医療費について |
| 心臓手術の医療費は、病名・手術の種類、術後の経過により変わりますが、自己負担が高額になることが多くあります。 健康保険の高額療養費制度を利用することで、自己負担額を抑えることができます。 高額療養費制度とは、1ヶ月の自己負担額の上限が所得に応じて決定され、申請をすることで自己負担額の上限を超えた分について払い戻しを受けることができる制度です。 限度額適用認定証を申請することで、窓口支払いの時点で自己負担上限額までの支払いとなります。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 70歳以上の方 基本的には限度額適用認定証の手続きは必要ありませんが、現役並みの所得がある方、非課税世帯の方は申請手続きが必要です。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 70歳未満の方 原則、限度額適用認定証の申請が必要です。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 18歳以上で心疾患により身体障害者手帳をお持ちの方 手術などによりその障がいが軽減され、機能が回復するような場合に、更生医療の制度を利用できます。医師の意見書などの書類をご準備いただき、居住地の役場に申請する必要があります。 ※利用する場合は、治療開始前に申請が必要になります。 ※原則1割負担となりますが、医療保険上の世帯の市民税額に応じて自己負担上限額があります。 ※市民税所得割額が一定以上の場合、支給対象外になります。 (令和6年5月)
|