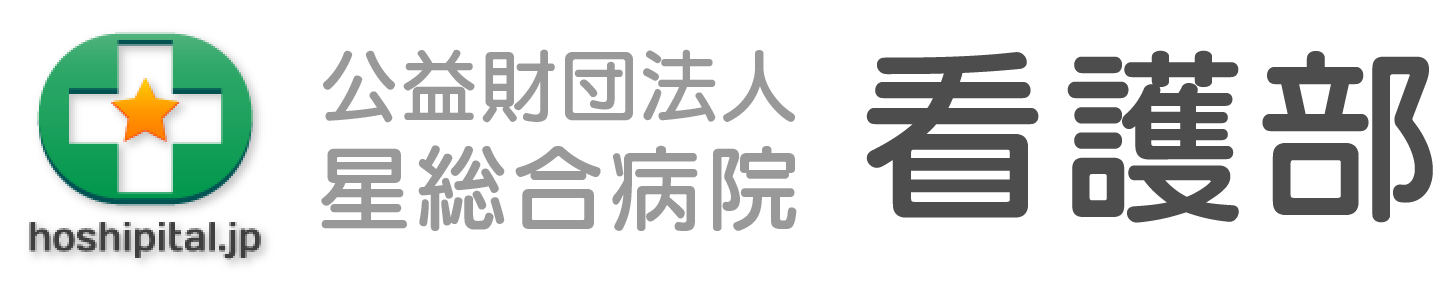スペシャリスト紹介specialist
認定看護師紹介
認定看護師とは、日本看護協会の行う認定審査に合格し、特定の看護分野において熟練した看護技術と知識を有することが認められた者をいいます。専門的知識に基づいた質の高い看護の実践および看護職員個人や集団に対し指導、相談の3つの役割を果たします。2025年4月現在、特定されている分野はA課程(21分野)とB課程(19分野)です。B課程では特定行為研修が組み込まれており、より高度な医療行為が可能です。当法人では、質の高い医療の提供をするため、より多くの認定看護師の育成に力を入れており、21名(2025年4月現在)の認定看護師が在籍しております。
当法人の高度専門資格者(認定看護師等)(2025年4月現在)
| 専門分野 | 所属 | 人数 |
| 皮膚・排泄ケア | 星総合病院 | 2名 |
| 感染管理 | 法人 | 1名 |
| 星総合病院 | 1名 | |
| 感染制御実践看護師 | 星総合病院 | 1名 |
| 認知症看護 | 星総合病院 | 2名 |
| 三春敬老園 | 1名 | |
| 緩和ケア | 法人 | 1名 |
| 星総合病院 | 1名 | |
| がん薬物療法 | 星総合病院 | 2名 |
| クリティカルケア | 星総合病院 | 1名 |
| 心不全看護 | 星総合病院 | 1名 |
| 在宅ケア | 法人 | 1名 |
| 摂食嚥下障害看護 | 星総合病院 | 2名 |
| 精神科看護 | 星総合病院 | 1名 |
| 星ヶ丘病院 | 2名 | |
| 乳がん看護 | 星総合病院 | 1名 |
| 合計 | 21人 | |
感染管理・感染制御 氏名(加藤和枝・根本文江・渡辺千香)
私たちは、専門的な知識と技術を用い、患者さんや来訪者、医療従事者など医療に関わるすべての人を感染から守るため活動しています。
感染対策は、一部の人が実施しても意味がありません。
星総合病院で働く全職員が「患者さんを守る、自分を守る、仲間守る」ことをモットーに、感染対策チームの一員として、正しく、効率的な感染対策ができるよう多職種と協働しています。
また地域全体の感染対策の質の向上を目的に、地域の医療機関と連携し互いに学び合い、より安全で安心な医療を提供できるよう感染対策に取り組んでいきます
。
-
- ●感染対策チーム、抗菌薬適正使用支援チームでの活動
- ●感染対策マニュアルの整備と周知
- ●研修会の計画および開催
- ●感染対策に関する各種相談対応
- ●職業感染対策
- ●アウトブレイク対応
- ●地域連携
がん薬物療法看護 氏名(郡司かおり・加藤久美子)
がん薬物療法を安全・安楽に実施するための管理や患者様のサポートが主な役割です。
抗がん剤治療の負担を軽くするため、ケアの提案や心のサポートなどを行っていますが、治療中であっても患者さんの望む生活を可能な限り実現させていける支援を心がけています。
また、がん薬物療法に関する看護スタッフの教育やがん医療の向上のための研究や社会貢献などに尽力する役割があり、院内研修をはじめ院外の講演活動、学会発表、イベント参加などを行っています。
抗がん剤開始前オリエンテーションおよび相談対応
化学療法室の運営と抗がん剤投与の実施
副作用に対するケアの提案、精神支援
化学療相談外来・電話相談(副作用の相談、治療の悩み、治療選択の迷いなど)
院内がん薬物療法の安全対策活動(化学療法委員会としての活動)
がん医療への貢献活動(院外講演、看護学校の臨時講師、がん関連イベントへの参加)
認定ゼミ「がん薬物療法看護」院内研修の講師(年5回シリーズ)
部署別勉強会の実施(依頼を受けて実施)
新薬・新治療の勉強会の実施
化学療法室内での看護実践モデルとしての教育 スタッフ育成
他施設から当院化学療法室研修生の受け入れ指導(web指導もあり)
ポートや末梢静脈点滴のトラブルに関する相談・副作用のケアに関する相談
がん薬物療法におけるインシデントに関する相談
患者サポートに関する相談
がん関連教育に関する相談
緩和ケア 氏名(久保木優佳・尾形育恵)
緩和ケア認定看護師は、重い病を抱え身体的にも精神的にも苦痛が生じた際に、その苦痛を出来るだけ和らげ、日常生活が穏やかに過ごせるよう患者さんやご家族に寄り添いながら支援していく役割があります。
緩和ケアは決して看取り時だけのケアではありません。治療期から必要なケアであり、生活の質を高めていくために必要なケアです。
重い病を抱えながらも生きたい生き方が選択できる、そして実現出来るようお手伝いさせて頂いています。
-
- ●緩和ケアチーム回診
- ●緩和ケア外来
- ●院内の教育ラダーの講師
- ●院外での高齢者施設等での看取りについての研修会の講師
- ●各科、スタッフからの患者相談
クリティカルケア 氏名(神尾悠美)
集中治療室に入室する患者様の病態の変化の予測や重症化の早期発見、重症化や合併症予防のための早期介入、生命維持装置や高度な医療機器の管理になります。
また、集中治療室に入室する患者様の状態変化を予測しアセスメントできる看護師を育成できるよう、スタッフ教育にも力を入れています。
-
- ●呼吸ケアチームとして呼吸器関連や呼吸ケアをサポートできるよう、多職種と連携してカンファレンスの実施
- ●ICU・HCUラダー教育
- ●急変対応シミュレーション
- ●各種研修会実施
在宅ケア 氏名(戸崎亜紀子)
訪問看護の対象は幅広く、地域で、在宅で、障害や疾病を抱えて暮らす人、その人を取り巻く人々もが対象となります。
多様な価値観をできるだけ尊重し、その人にとって何を大事にするべきか考えながら、支援することを心掛けています。
-
- ●当法人の在宅事業に関する部署の後方支援
- ●在宅医療や訪問看護関連の研修講師
- ●オレンジカフェ(認知症カフェ)
- ●地域の医療介護福祉職の顔の見える関係作り(懸け橋メイトミーティング)
- ●医療介護職向けどこでもメディカルセミナーのコーディネート
心不全看護 氏名(李民純)
心不全は再発しやすく増悪予防のためには患者のセルフケアを支援することが重要です。
しかし、「心臓だけに問題がある」心不全患者は少なく、患者ごとに多様な生活模様があり、通り一辺倒に指導することはかえって患者のQOLを低下させることになります。
そのため多面的に患者をアセスメントし、多職種と協働して、リアルな生活の中で心不全増悪予防ができるように支援することを大切にしています。
また、セルフケア支援とは「患者がどう生きたいか」を支える支援です。
患者にこれまでの人生を語っていただき、何に価値をおいているのかを見定め、多職種と共有し「その人らしく生きるためのセルフケア支援」の実現ができるように活動をしています。
-
- ●外来における心不全患者へのセルフケア指導
- ●病棟、在宅スタッフとの心不全患者の連携(ICTツール使用)
- ●医師、薬剤師、理学療法士、栄養士、病棟看護師、MSW、在宅スタッフたちとの多職種カンファレンス(週に1回)
- ●心不全チーム会議(ハートサポートプロジェクト)
- ●心不全地域連携パス作成と運用
- ●心不全緩和ケア
- ●地域の医療スタッフ、介護スタッフへの啓発活動や研修会の実施
- ●院内研修など
摂食嚥下障害看護 氏名(菊池知美)
人には生活するために必要な要素が幾つかあります。そのうちの一つが「食事」です。これらの生活の要素はそれぞれが関連し合っています。
摂食嚥下障害看護では、摂食嚥下障を抱える患者さんの“強み”を活かし、「美味しく、安全な経口摂取」を目標に看護の専門性を活かしたケアを提供しています。
急性期では、治療のための体力作りを第一に、多職種と連携し栄養管理を中心としたケアを提供しています。
回復期では、退院後の生活環境を考慮した、食事形態や代償法、退院指導を中心としたケアを提供しています。すべてのケアは「食事」に繋がっています。
患者さん寄り添った“食べる”を支える看護を提供していきたいと思います。
-
- ●NSTカンファレンス・回診
- ●摂食嚥下支援チームカンファレンス・回診
乳がん看護 氏名(佐藤亜由美)
乳がんの対象はAYA世代から高齢者まで幅広く、治療は長期にわたります。
乳がん看護認定看護師は、乳がんと診断された患者さんやそのご家族に対し、家庭や仕事、妊孕性、セクシュアリティなど病気による生活上の影響を共有して、生活の質(QOL)を維持向上できるよう支援します。
また、多職種と連携して、副作用への対処、ボディイメージの変化へのサポート、看護スタッフへの支援等の役割を担います。私は、患者一人ひとりが「大切にしていること」を理解し、自分らしく生活できるよう支援することを日々心がけています。
乳がんと共に生きる力を引き出し、高めていくケアが提供できるように努めてまいります。どうぞ、気軽にお声がけください。
-
- ●患者・家族への乳がんに関する情報提供・治療選択への意思決定支援
- ●アピアランスケア(乳房補整具、下着等)、セクシュアリティの相談
- ●患者・家族へ乳がん術後の退院指導、生活相談
- ●リンパ浮腫予防への支援
- ●多職種と連携したチーム活動
- ●創部ドレーンの抜去(特定行為)
- ●乳がんの周術期患者のケア、副作用マネジメントや疼痛緩和に関する看護スタッフへの支援
- ●医療スタッフに対する乳がん看護の知識、技術に関する相談
- ●ピンクリボンを通じた乳がん啓発活動
- ●患者会の運営(さくら野会)
認知症看護 氏名(田辺晃子・三本木由香里・大河原靖子)
超高齢社会を迎え、認知症の方が医療を受ける機会も増加しています。
認知症の方は、記憶障害や理解力の低下などにより様々な不安を感じながら生活されています。
入院することで、いままで生活してきた場所とは異なる慣れない療養環境や、苦痛を伴う治療や処置によって、混乱を招きやすくなります。
また、ご自身の思いや困りごとを言葉で表現することが難しい方もいます。
不安な気持ちに寄り添い、その方が何を思っているのか、困っていることは何なのかをスタッフと一緒に考え、認知症があっても、安心して入院・療養生活を送れるようにお手伝いさせていただきます。
-
- ●認知症ケアチーム活動(ラウンド、カンファレンス、勉強会開催)
- ●精神科リエゾンチーム活動(ラウンド、カンファレンス、勉強会開催)
- ●身体拘束の評価、最小化にむけての取り組み
- ●もの忘れ外来
- ●院内研修講師(ラダー研修等)
- ●院外研修講師(看護協会講師活動、看護学校講師、どこでもメディカルセミナー)
- ●市民講座講師
- ●認知症カフェ、健康教室講師
- ●認知症看護に関する実践・指導・相談(病棟・外来・施設内)
皮膚・排泄ケア 氏名(永崎真利子・斎藤敦巳)
私達の分野は大きく3つの領域(WOC)から成り立っております。
W「創傷」:褥瘡(床ずれ)、傷、瘻孔などの創傷の予防と治療、スキンケアなどを行います。
O「オストミー・ストーマケア」:ストーマ(人工肛門・人工膀胱)のケア、装具の選択と装着、日常生活の指導などを行います。
C「失禁ケア」:便や尿のコントロール、失禁による皮膚トラブルの予防とケアなどを行います。
専門性を発揮し、生活の質が高められるようセルフケア支援など質の高いケアを提供しております。
皆様が住み慣れた環境で笑顔で過ごせるように、地域との懸け橋となり切れ目のない看護を継続できるように目指しております。
-
- ●褥瘡回診
- ●排尿ケア回診
- ●ストーマ外来
- ●スキンケアの相談
- ●看護師特定行為実践(創傷管理関連)
- ●同行訪問看護
- ●院内外の教育
- ●市民向けの研修会・公開講座
- ●学会参加・研究発表など
精神科看護 氏名(半谷修一郎・若林千恵・八巻美恵子)
精神科認定看護師は、精神障がいを抱える方やその家族に寄り添い、その人らしい回復を支える専門職です。
治療への不安や悩みだけでなく、障がいによって希望を失うことがないよう支援し、入院から退院後の地域生活への移行・定着まで切れ目のない支援を行います。
また、根拠を基づいた看護を実践し、スタッフへの相談支援や教育を通じて看護の質の向上に努めます。
私が大切にしていることは、精神障がいを持つ方と「人と人」として向き合い、その人らしく生きる姿を見守り、応援することです。多職種で地域の支援者と連携し、共に考え、悩み、喜びを分かち合いながら、あたたかく、柔らかい支援を心がけています。
-
- ●精神科病棟での看護や退院支援
- ●精神科外来での相談業務
- ●行動制限最小化への取り組み
- ●地域の精神障がい施設等の相談業務
特定行為研修修了者紹介
特定行為とは、診療の補助であり、医師の直接的指示で実践できる医療行為又は事前の手順書(包括的指示)により看護師の判断で実践できる医療行為のことです。
特定行為研修とは、共通科目とされる医学的基礎知識(臨床病態生理学、臨床薬理学、臨床推論等)の研修を修了し、区分別科目として特定行為に関する実践的な理解力、 思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能を習得します。
当法人では、69名 延べ91名 14区分(2025年4月現在)の特定行為研修修了者が在籍しております。 それぞれが試行錯誤しながら自身の役割を見出し、より良い医療・看護の提供のため、最善を尽くしたいと考えております。
修了者の目指す姿として、「患者に寄り添った看護の中でアセスメント力を発揮し、医師との連携の下タイムリーに医療を提供でき、 医療チームのキーパーソンとなることで、『全身で看護する』を実践する」としています。
当法人の高度専門資格者(看護師特定行為研修修了者)(2025年4月 現在)
| 特定行為区分 | 特定行為 | 修了者数 (延べ数) |
| 創傷管理関連 | 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 | 21名 |
| 創傷に対する陰圧閉鎖療法 | ||
| ろう孔管理関連 | 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 | 10名 |
| 膀胱ろうカテーテルの交換 | ||
| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 | 21名 |
| 脱水症状に対する輸液による補正 | ||
| 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | 抗けいれん剤の臨時の投与 | 24名 |
| 抗精神病薬の臨時の投与 | ||
| 抗不安薬の臨時の投与 | ||
| 感染に係る薬剤投与関連 | 感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与 | 6名 |
| 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整 | 1名 |
| 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 侵襲的陽圧換気の設定の変更 | 1名 |
| 抗非侵襲的陽圧換気の設定の変更 | ||
| 人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整 | ||
| 人工呼吸器からの離脱 | ||
| 循環器関連 | 一時的ペースメーカの操作及び管理 | 1名 |
| 一時的ペースメーカリードの抜去 | ||
| 経皮的心肺補助装置の操作及び管理 | ||
| 大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うときの補助の頻度の調整 | ||
| 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 | 中心静脈カテーテルの抜去 | 1名 |
| 創部ドレーン管理関連 | 創部ドレーンの抜去 | 1名 |
| 動脈血液ガス分析関連 | 直接動脈穿刺法による採血 | 1名 |
| 橈骨動脈ラインの確保 | 1名 | |
| 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | インスリンの投与量の調整 | 1名 |
| 術後疼痛管理関連 | 硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整 | 1名 |
| 循環動態に係る薬剤投与関連 | 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整 | 1名 |
| 持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整 | ||
| 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 | ||
| 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整 | ||
| 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整 |
修了者①
褥瘡や創部をアセスメントする力も必要であるが、それだけでなく全人的な見方を養う事の重要性が更に身につきました。
特定行為研修を受講したことで実践力の高い知識や技術が得られ、医師からの指示待ちで処置が遅れないよう、タイムリーな看護の提供や初期対応を実践し、多職種と協働する事で退院後も継続した看護実践に務める事ができます
。
-
- ●デブリードマンの実施
- ●褥瘡患者における患者・家族・スタッフへの教育 など
修了者②
患者の症状を臨床推論で考えるようになり、輸液投与の危険性を学び、投与の基本を意識するようになりました。
自分に何ができるのか、より自己の役割をより考えるようになりました。
-
- ●勉強会の講師
- ●経口摂取困難な抗がん剤投与における倫理カンファレンスの開催 など